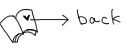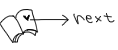第一話:秘密結社エム会 vs エコ戦隊ナビレンジャー
学園の王子様、そんなあだ名を付けられた痛々しい奴がいる。
外見は確かに王子様だ。艶のある金髪に青い瞳。彫りの深い顔立ちなので、その容姿に違和感はない。本人談によると、奴の祖父にあたる人物がイギリス人で、その血を濃く継いだのだとか。金髪碧眼という容姿は校内では希少価値が高いため、奴の存在は(悪い意味で)とびきり目立っている。目立っているからこそ、王子様というぶっ飛んだあだ名が付けられたのだろう。奴を見かけると多くの女子生徒たちはうっとりする。中には爽やかな笑顔とウインクにあてられ、失神するバカもいる。何度かその光景を見かけたのだが「趣味が悪い」というのが男の僕の、正直な感想だった。
雰囲気はとびきり甘く、物語に出てくる白馬の王子様そのものと一部の女子生徒に称される奴は、実は密かに風紀委員会に目をつけられている問題児でもある。これは友人の風紀委員長に聞いた話だが、奴は無類の女好きらしい。なんでも一日一人、女子生徒を詐欺師のように(本人は真面目なようだが)口説いては保健室や体育館倉庫にお持ち帰りしているのだとか。当然、真面目な風紀委員会は王子様が女の子に手をだそうとするたびに生徒指導室に補導している。
そんな王子様は、この秋から生徒会副会長として日々多忙な生活を送っていた。僕がいなければ、奴が生徒会長という座についていたかもしれない。……それを防げただけでも、僕の存在価値はあった。奴が生徒会長になっていたらと考えると――それだけでおぞましい。正直、生徒会長になるまで奴のことは知らなかったが、会長になってからは嫌というほど、その性癖を目の当たりにするハメになった。
過去に一度、僕は奴の女たらしの性癖を言及したことがある。風紀委員長に昼ごはんを奢ってもらった代償として(正確にははめられた)、副会長になっても一向に改善する様子のない王子の「お持ち帰り癖」を諌めることになったのだ。僕としては人の目につかないところでならどうぞイチャイチャしてくださいと言いたいところだが、堅物の風紀委員長がそれを許さない。「女の子に対する冒涜だ」とか言って、生徒会長たる僕に打診してきやがった。巻き込むなよ、と食べた後ではさすがに言えない。そうしてしぶしぶ「生徒会の恥になるから、女の子に手を出すのは自重してくれ」と奴に話した、そのときの、返答。
「俺がお嬢さんに手をだすような真似をするはずがないじゃないか。なぜなら紳士だからね。手は出していない。それなのに風紀委員長は、俺を悪者にしようとしているのかい? ……ああ、それはなんと嬉しいことだろう! 労力をかけずに、いたぶられるフラグを立てることができるだなんて」
「……は?」
一言一句違わず覚えている。僕は思わず耳を疑ったが、この台詞を言ったときの王子様の頬は(背筋に悪寒が走るほど)紅潮していた。思い出すだけで身の毛がよだつ話しだが、あいつは、きっとどこかのネジが外れてしまった可哀想な王子様なのだろう。
「悪者、俺が悪者。ねぇ、じゃあ本当に女の子を襲えば、俺は委員長によって厳しいお仕置きを受けることになるのかい? それはいいね。いい、最高だ! あのお嬢さんは手が早いから、きっと殴られる!」
こんな奴が生徒会長になるくらいなら、まだ僕の方がマシだろう。本気でそう思えた瞬間だった。
「冬夜! 待てって言ってるでしょ。聞こえてないわけ?」
スタスタ家路を歩いていた僕は、急に後ろに引っ張られて少しよろめく。お仕置きの素晴らしさを語る王子様の荒い息遣いをリアルに思い出して、気分が悪い。機嫌も悪い。
「なに? 早く帰りたいんだけど」
いつの間にか、僕はたまたま帰り道で遭遇した風紀委員長こと如月香世に腕を掴まれていた。
女のくせに力が強い。腕がキリキリ痛む。僕は露骨に顔をしかめるが、香世は顔など見ちゃいなかった。
「あれ……見たことある後ろ姿じゃない?」
「ねぇ、痛いんだけど」
「あの金髪。まさかとは思うけど」
「離せよ、香世」
「光ヶ丘じゃないの?」
「――は?」
「ほら、あれ。あそこで……足蹴りされている痛々しい人」
腕の痛みもつい忘れて、香世が指さす方向に顔を向けた。
ここは、児童公園のはずだ。夕方の時間帯なので多くの子供とその保護者で賑わっている、平和な児童公園のはずだ。そんな場所に過激な性癖を持つ学園の王子様こと光ヶ丘雅也が存在するはずがない。と僕は断言したかったのだが、たしかに、児童公園の一角に見るからに浮いている二人組がいる。一人は他校の制服を着た茶髪の青年で、僕の記憶には全くない人物だ。しかしその人物の隣、正確には足の下にいる金髪には見覚えがある。着ている制服も、僕と同じ。
「……なんてものを見つけるんだ、お前は」
「たまたま視界に入ったの。つーかさ、あれ、何やってんの?」
「僕にはSMショーにしか見えないが」
「あれが副会長だなんて知られたら、学校全体の恥にならない?」
「だから真面目な風紀委員長、がんばって取り締まってきてね」
「は? バカ言わないで。副会長はあんたの部下みたいなもんでしょ。部下の不始末は上司の不始末」
「あいつを副会長に選んだのはバカな女どもであって僕じゃない」
「会長ならもっと責任を持つべきじゃない?」
「そんな責任持ちたくない。というか、なんか、形勢逆転してないか?」
僕と香世が色々と口論している間に、何かしらの進展があったようだ。いつの間にか茶髪の青年が地面に転がっており、立ち上がった光ヶ丘が高らかに笑っている。状況が変わったとはいえ、夕方の公園に相応しくない異様な光景だ。二人の痛々しい高校生に近寄ろうとする子供を、保護者は慌てて遠ざけている。中には公園から出ていく親子の姿も何組かあった。
本当に頭が痛くなる。何をやっているんだ、あのバカは。
「ねぇ、公園の反対側に回れば、あのバカの声聞こえるんじゃない?」
「聞きたいのか?」
「何やってんのか気になるじゃん」
「……それもそうだな」
確かに、関わりたくはないが何をやっているのかは気になる。生徒会長として彼と嫌でも付き合っていかなければならないため、後学のために見ておくのもいいだろう。
香世が足早に歩き出したので、僕もそれについていくことにした。
「ふふふ、これまでだな」
「なっ、何を……」
「このあたり一体の雑草はすでに我が手の内にある。つまり、この区域で酸素を出し続けていた存在は消滅したのだ! やがてここには二酸化炭素が充満し、地球温暖化が進行することだろう。そうすればみんな苦しむことになる。存在するだけで苦痛を味わうことができるのだ」
確かに光ヶ丘の手には雑草が握られているが、そもそも公園は管理の行き届いた場所なので元から生えている草が少ない。草が少ない以前に、それっぽっちの雑草を引っこ抜いたことと地球温暖化がどう関係してくるのだろうか。
「これで俺は快楽に溺れることができる!」
夕方の公園で、しかも子供で賑わう場所で叫ぶようなことではないだろ。同じ制服を着ているということがなんだか恥ずかしくなってきた。子供たちが何事かと遊びの手を止めるが、その保護者たちが素早くかわいいわが子を抱いて公園から逃げ出していく。
「お前の企みは、絶対に、絶対に阻止してみせる!」
「ほお、阻止できるものなら、阻止してみるがいい」
「してやるさ。――見ろ、これが僕の、本当の力だ!」
茶髪の青年が、奇抜なダンスを踊り始めた。いや、格好をつけ始めたとでも言うべきか。彼も光ヶ丘に負けないくらい、なかなか痛々しい。
「へーんしん!」
そんな台詞と同時に、お祭りの屋台でよく見かけるヒーローもののお面を装着する謎の青年。
思わず吹いてしまった。隣で香世が声を殺して肩を震わせている。目には涙が溜まっていた。
「なっ、貴様、まさか!」
「そうさ。エコ戦隊ナビレンジャーとは俺様のこと。情熱に溢れるレッド、ここに見参!」
なんだその奇抜なネーミングは。というか、この人も相当あれだ。ネジが外れている。
「ふ、こんなところで出会うとは、これもまた運命。ここで消えてもらおうか。いーっ」
「お前を倒して、地球を守ってみせる! ――とお!」
戦闘シーンには容赦なかった。
お面の青年が光ヶ丘目掛けて膝蹴りを放つ。もともと運動神経のよろしくない光ヶ丘は、鳩尾に入った懇親の蹴りによって本当に痛そうな声を出しながら地面に崩れた。その背中に、青年が足を乗せる。僕のいる位置から光ヶ丘の表情が見えるのだが……なんだか、幸せそうだった。
「はーっははは、エム会、思い知ったか」
「くっ、くそ、覚えていろ、ナビレンジャー!」
エム会? 最初はピンとこなかったのだが、隣の香世が「まさか、マゾのエム?」と呟いたのを聞いて納得した。ますます子供たちに見せてはならない光景だ。もっとも、公園にたくさんいた子供たちの姿は半減している。残った子供たちも遊びに夢中で、幸いなことに奇抜な二人組の奇怪な行動には目も向けていない。
青年二人はしばらくの間そのまま突っ立っていたが、やがて茶髪の青年がお面をはずし、足をのける。光ヶ丘も一度立ち上がり、二人は地べたに座って首を傾げ始めた。
ちなみにふと隣を見ると、笑い疲れてぐったりしている香世の他にもう一人、あの茶髪の青年と同じ制服を着た青年が呆然と立っている。
「ふーむ、なあ、雅也。どこが悪いのだと思う?」
「アクションシーンが、今ひとつだったのかもしれない」
そこじゃない。というか、あれを子どもに見せるつもりだったのか。警察に捕まるぞ。
「あー、でもそれは、お前がすぐやられてしまうのが悪い」
「秋葉が本気でかかってくるのがいけないんじゃないか」
「じゃあ、きっと人が足りないんだな!」
「それは俺も思ったぞ」
「せっかくのレンジャーものなのに、俺一人しかいないというのが問題だ。レンジャーは三人組か五人組というのが相場だからな」
「悪役も、大勢いなければすぐにやられてしまう。きっと、子供たちが見てくれないのはそのせいなんだ」
見当違いも甚だしい。子供たちに見てもらいたいと思うのなら(そして通報を防ぐためには)、深夜番組のような内容を朝の内容に変えるところから始めるべきだ。
「じゃあ、お互い次の週までに人材を補給するというのはどうだろう? ちょうど俺の学校の生徒会にいい素材がいてね。次回はブルーとピンクを連れてくるよ」
びくっと、香世の隣で盛大に青ざめる好青年。
「おお、それなら俺は、悪役の同士をたくさん引き連れてくることにしよう。俺のところの生徒会長は、細身のくせに喧嘩強いことで有名なんだ。きっとアクションシーンに華が出るよ」
今度は僕が盛大にフリーズした。
「へぇ、それは楽しみだな」
「ああ、俺も君の同志に会うのを楽しみにしているよ」
血迷ってもあんな茶番劇に付き合うつもりはない。
「……巻き込まれるのはごめんだ」
「……冗談じゃない」
香世の隣に立っている青年と声が重なり、互いに顔を見合わせた。
どうやら彼は、あの茶髪の青年と知り合いらしい。可哀そうなほど青ざめた顔をしている。
「あの人の知り合い?」
「…………あれでも、うちの学校の生徒会長なんです」
「それは気の毒に」
「ええ、もう本当に」
僕も、一歩間違えれば、生徒会選挙で本気になっていなければ、彼と同じポジションに立たされていた可能性がある。おぞましすぎる。
「ねえ、冬夜」
「なに?」
「光ヶ丘、なんかこっち見てるんだけど。あと、その、そっちの生徒会長さんも」
ハッと慌てて視線を戻すと、バカ王子と視線が合ってしまった。
僕はしばらく硬直する。彼は笑顔だ。ものすごく爽やかな、王子様と見紛うほどの笑顔だ。
「やべっ」
「――っ逃げるぞ、香世!」
「了解」
冷や汗の量が尋常じゃない。
学校でならのらりくらりと交わせるが、現場で捕まってしまえばそれだけであの奇妙な集団の仲間入りだ。僕は変な目で見られたくない。生徒会長としての誇りもある。
僕と香世は右側へ走り出し、あの好青年は左側へと走り出す。
先の長い生徒会の未来に、一抹の不安を感じた瞬間だった。